保育料
毎月の保育料の額は、世帯の市民税額等により、階層区分に分けて決定します。
保育料の決定について
毎月の保育料は世帯の市町村民税所得割課税額等に基づき、年2回算定します。
令和7年4月から8月分
令和6年度市民税所得割課税額に基づく(令和5年1~12月の収入等で計算)
令和7年9月から令和8年3月分
令和7年度市民税所得割課税額に基づく(令和6年1~12月の収入等で計算)
令和7年度保育料徴収基準表
3~5歳児クラス(令和7年4月1日現在3~5歳)の保育料は無料です。
保育料徴収基準額表の見方(公立・私立共通)
- 入所児童の年齢を確認します。(令和7年4月1日現在の年齢)
- 父・母の市民税所得割課税額を足した額が当てはまるところを基準額表で確認します。
- 入所児童が何人目か確認します。
保育料の算定基準となる市民税所得割課税額について
市民税所得割課税額については、会社員等の方は雇用主から配付される下図の市・県民税の通知書の「(4)税額控除前所得割額」をご覧ください(それ以外の方は1月1日にお住まいの市区町村の住民税担当課へお問い合わせください)。両親分の「(4)税額控除前所得割額」の額を合算した額が基準額表中の階層区分のおおよその目安となります。
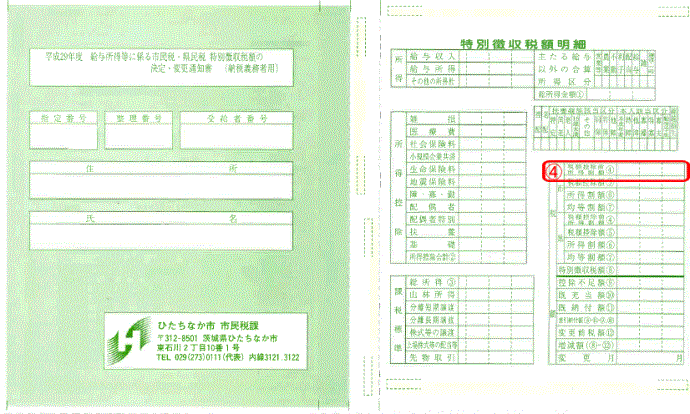
保育料のお支払いについて
[お支払い方法]口座振替
[引落日]毎月28日(金融機関が休みの場合は翌営業日)
保育料を滞納された場合は下記の内容を実施しています。
- 督促状、催告書の通知
- 保育所(園)からの納付指導
- 申し出による児童手当からの保育料の徴収(市の歳入の確保と納付している多くの方々との公平性を図るため、児童手当を受給している保護者が保育料を滞納している場合は、保護者の申し出により児童手当から徴収する制度を実施しています。)
- 自宅及び就労先への訪問
- 児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく滞納処分(給与、不動産、預金等の財産を調査し、差押えをする場合があります。)
注意点
- 月の途中で退所する場合や、入所決定後に辞退期限を過ぎてから辞退を申し出た場合は、一か月分の保育料が発生します。
- 延長保育料や教材費等は別途必要です。保育所(園)によって異なりますので、詳しくは施設にお問い合せください。
- 婚姻や離婚等で世帯状況に変更があった場合や市民税所得割額に変更があった場合は、保育料が変更になる可能性があります。世帯状況等に変更が生じた場合は、お申し出ください。
よくあるご質問
Q.保育所(園)の入所を希望しています。入所した場合の保育料はいくらになりますか?
A.保育料は市民税課税状況や世帯状況、軽減措置制度の該当の有無より複合的に算定するため、保育所(園)の入所決定前にお答えすることはできません。
Q.3歳の誕生日を過ぎたら、保育料は無料になりますか?
A.2歳児クラスのお子様が年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、保育料は無料になりません。3歳児クラス(4月1日時点で3歳)から無料になります。
Q.保育料の引き落としができず、自宅に督促状が届きました。どうしたらよいですか?
A.口座振替ができなかった月の翌月の10日頃に、入所されている保育所(園)を通じて、納入通知書を配付します。納入通知書により、督促状および納入通知書に記載された期限までに、指定の金融機関や取り扱いコンビニエンスストア等でお支払いください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1964
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
